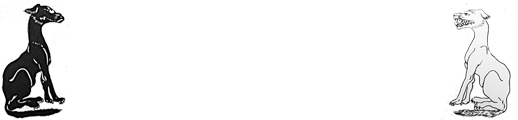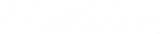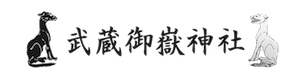御岳山山頂(標高929m)の境内に、本殿・拝殿をはじめ数々の神を祀るお社があります。
本殿奥の玉垣内にある各社には、9時から16時まで自由にご参拝いただけます。(祭礼のため閉鎖する場合があります)
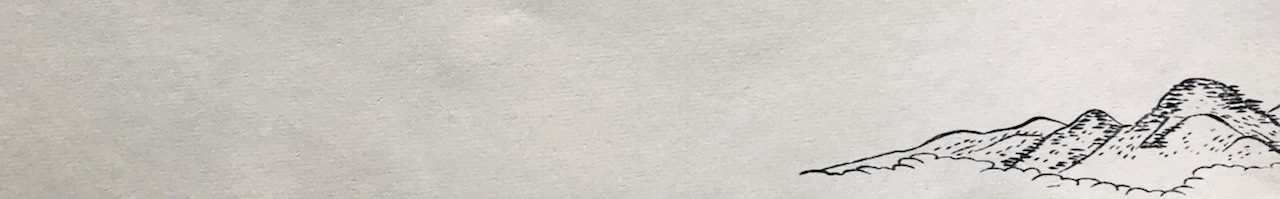
境内社
由緒ある数々のお社が、御岳山の山頂に
-

本殿
武蔵御嶽神社・本殿(ほんでん)の御祭神は、 櫛麻智命(くしまちのみこと)、大己貴命(おほなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、廣國押武金日命(ひろくにおしたけかなひのみこと ※)。
随所に菊の御紋をいただく当社殿が造営されるまでの社殿(旧本殿)は玉垣内に移築され、「常磐堅磐社」として祀られています。※ 廣國押武金日命は、神仏習合の教説で「蔵王権現」と同一の神格とされています。
神明造/明治11(1878)年造営
-

幣殿・拝殿
幣殿・拝殿(へいでん・はいでん)は、徳川治世となって江戸の「西の護り」として東向きに改築され、現在も東京の街を見守る本殿の前に位置します。
元禄13(1700)年に5代将軍綱吉の命によって改築され、修復を重ねながら今も大切に使われています。入母屋造/元禄13年改築・天保に修復、明治中頃に檜皮葺から銅板葺屋根
-

大口真神社
大口真神社(おほくちまがみしゃ)の御祭神は、大口真神。
御祭日は、1月3日・5月15日・9月29日。
かつて山中に迷われた日本武尊は、道を拓き導いた狼に「 "大口真神" としてこの山に留まり、すべての魔物を退治せよ」と仰せられました。特に江戸時代からは諸災厄除・盗難・火難除の守護の神として神符を「おいぬ様」とあがめ、戸口に貼る、敷地にお社を建てるなど、家の守り神とする信仰が広まりました。流造・瓦棒銅板葺
-

常磐堅磐社(旧本殿)
常磐堅磐社(ときはかきはしゃ)の御祭神は、全国一の宮の神々等・八十七柱。
本殿として永正8(1511)年に一間社流造・銅板葺きの桃山様式で創建された、歴史を伝える貴重な建造物です。明治10(1877)年に現在の本殿に建て替えられた際、移築されて「常磐堅磐社」となりました。
国指定重要美術品。昭和27(1952)年11月3日、東京都指定有形文化財に指定。
令和3年3月、漆の塗り替え工事を完了しました。流造・桧皮葺型銅板葺/永正8(1511)年建立
-

皇御孫命社
皇御孫命社(すめみまのみことしゃ)の御祭神は、天瓊々杵命(あめのににぎのみこと)。"天地が豊かに栄え、稲穂が豊かに実る国の壮健な男子"という御名の神。天孫降臨神話の主役で、皇室の基礎の神とされます。
社殿は複雑な屋根の軒先に「三葉葵」の紋があり、かつては東照社の社殿であったことがうかがえます。
令和3年2月、腐朽修理工事にともない、屋根を「瓦棒銅板葺」から創建当初の姿に近い「平葺」へと葺き替えました。入母屋造・千鳥破風付・向拝軒唐破風造・銅板/江戸後期
-

東照社
東照社(とうしょうしゃ)の御祭神は、徳川家康公(とくがわいえやすこう)。
当社を江戸の「西の護り」とし、長く平安の世となる基礎を築いた江戸幕府の初代将軍・徳川家康公の御霊をお祀りしています。
御扉には、徳川家の家紋である「三葉葵」の紋があしらわれています。流見世棚造・銅板葺
-

巨福社
巨福社(こふくしゃ)の御祭神は、埴山比女神(はにやまひめのかみ)。農作物を豊かにしてくれる土の神です。
古来、巨福社の周りの土は霊験が強いとされ、"持ち帰って畑などに撒くと虫などの害を防ぐ"という信仰が伝えられています。方位除・厄難消除の御砂としてもあがめられています。
「御砂」は神符授与所にて頒布しています。流造・桧皮葺型柿葺
-

神山霊土歌碑
"この神山の土の霊力が虫などの様々な害を防ぐ"という御神徳が刻まれた歌碑です。
題字 : 副島種臣 / 外務卿
詠 : 本居豊頴 / 歌人、本居宣長の曾孫
書 : 山岡高歩(鉄舟) / 政治家、思想家、剣・禅・書の達人明治20(1887)年 2月建立
-

北野社
北野社(きたのしゃ)の御祭神は、菅原道真公(すがわらのみちざねこう)。
「天神様」と親しまれ、学問向上を願う人々の信仰を集めています。また、書・筆・文具などを奉納し、文筆の向上を願う人もいます。流見世棚造・瓦棒銅板葺
-

神明社
神明社(しんめいしゃ)の御祭神は、天照皇大御神(あまてらすすめおほみかみ)、豊受比賣神(とようけひめのかみ)。
「神明様」と呼ばれ信仰される伊勢の神宮の神霊をお祀りしています。神明造・向拝付・銅板葺
-

二柱社
二柱社(ふたはしらしゃ)の御祭神は、伊邪那藝大神(いざなぎのおほかみ)と伊邪那美大神(いざなみのおほかみ)。
この神話で最初の夫婦神が、あまたの国生み・神生みを行い、世界が生命力にあふれ変化に富む豊かなものとなったことから、生命の祖神とされています。流見世棚造・銅板葺
-

八柱社
八柱社(やはしらしゃ)は、春日社(かすがしゃ)、八幡社(はちまんしゃ)、●養社(こかひしゃ)、八雲社(やくもしゃ)、●摩社(ゐがずりしゃ)、月乃社(つきのしゃ)、國造社(くにのみやっこしゃ)、八神社(はっしんしゃ)の総称。
※「こかひしゃ」の一文字目は、「神」の下に「虫」
「ゐがずりしゃ」の一文字目は、「座」の左の「人」の位置に「口」流見世棚造・銅板葺
山内のお社
山頂だけではなく、参道途中などの山内にもお社があります。
-

三柱社
三柱社(みはしらしゃ)の御祭神は、大歳神(おおとしのかみ)、御歳神(みとしのかみ)、大山咋神(おおやまくいのかみ)。
豊年・豊作をあらわす"歳神"と、家運隆盛・水源の守護を司る"山の神"をお祀りしています。流見世棚造
-

稲荷社
稲荷社(いなりしゃ)の御祭神は、倉稲魂神(うかのみたまのかみ)。
御祭日は二月の初午の日。日々食物に困らず、商いできることに感謝し、山の民が集う稲荷社祭が執り行われます。流見世棚造
-

随身門
明治期のいわゆる神仏分離(神仏判然)以前は、仁王門であったと伝えられています。
-

疱瘡社
疱瘡社(ほうそうしゃ)の御祭神は、山末大主神(やますゑのおほぬしのかみ)。
「疫神社(えやみのかみしゃ)」とも呼ばれ、御神域である山内に疫病などの穢れが入らぬように、防いでいただけますようにと祀られています。流見世棚造