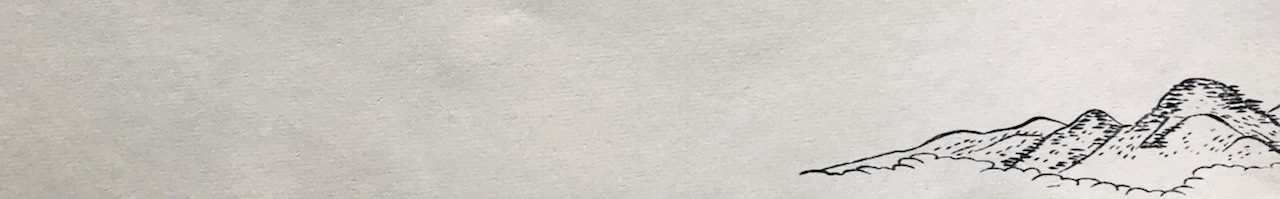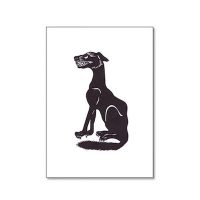Q:御師とは何ですか?
A:
「御師」とは、伊勢では「御師=おんし」と称し、御祈祷師を略したものと言われています。
伊勢の外では「御師=おし」と呼ばれています。
かつて神職は神明奉仕のみに勤めるものとされ、信仰を広めたり、個々人の細やかな願事を祈ることはできませんでした。
対して御師は、神職でありながら、訪れる人の案内、ご祈祷、さらには宿をも提供し、参詣にまつわる全般の世話を行ったとされます。関東近県では、筑波、赤城、榛名、戸隠、三峯、富士、大山などの霊山にある神社に御師があらわれ、信仰を広めていきました。
当社の御師は、特に春には御嶽講中の参拝の世話を行い、特に冬には山を下り、講のある村・町へ出向いて講に所属する家々に御札を配って廻っています。
現在でも数ヶ所の神社に御師は存在しますが、昔ながらの活動を活発に続けているのは、当社の御師と御嶽講だけとも言われています。
Q:講とは何ですか?
A:
「講」とは、さまざまな組織の団体のことをいい、「御嶽講」は武蔵御嶽神社を信仰する、各地の村や一族などの集団です。
昔は字(あざ)などを単位とし、その字名を冠して「○○御嶽講」などといい、その活動は、講を構成する家から集めたお金(古くは米や五穀)で、数人の代参人(講全員に代わり参拝する意)を選び、神社参拝を行いました。
信仰だけでなく、物見遊山や娯楽、またここには各地より人が訪れているため、情報交換の場ともなっていました。
干ばつや台風、害虫に強い稲などを持ち寄ることも行われ、情報の少ない時代の重要な組織として爆発的に広がりました。
現在でも春には代参人が神社参拝をし、また秋から冬にかけては御師が講に出向き、一軒一軒お札を配り、家によっては神棚祈祷も行っています。
江戸中頃より広まった講組ですが、その永続と参拝を記念して奉納された大きな石碑が参道に立ち並んでいます。
刻まれた地名を見れば、武蔵御嶽神社の信仰が関東一円に広がっていることが分かります。