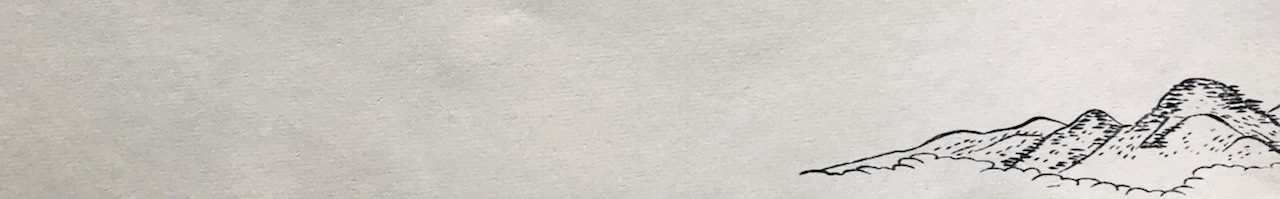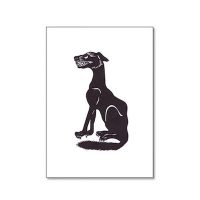Q:菊の御紋があるのはなぜですか?
A:
幕末、関白・二条斉敬(にじょうなりゆき)公より清和天皇祭祀の通知があり、当社が「二条家祈願所」として選ばれたことにより、菊の御紋の使用が許されました。
しかし、明治新政府により菊の御紋の使用禁止令が出たため、使用できなくなりました。
明治新政府の神社を国家の宗祀とする施策による、神仏分離を伴う神社制度改革のなかで、「社格にあわせた社殿建築」に統一する動きが進み、当社も明治10(1877)年に神明造りの本殿と建て替えられ、現在に至ります。
この経緯のなかで、「皇居の西の守り神として崇める」という有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王の意向が働き、あらためて正式な表御紋(十六弁の菊)の使用が許されたのでした。
なお、建て替え前の旧本殿は境内に移築され、「常磐堅磐社」として現存しており、
歴史を伝える建造物として、国指定重要美術品かつ東京都指定有形文化財に指定されています。
(詳しくは → 境内社 もご参照ください。)
二条斉敬
文化13年(1816)9月12日11月1日生~ 明治11年(1878)12月5日没
幕末の公家政治家。五摂家。父は斉信,母は水戸藩主徳川治紀の娘従子。
安政5(1858)年条約調印に反対の態度を示し,12月,徳川家茂への将軍宣下を伝達のため江戸に赴く。文久2(1862)年1月に右大臣,同12月国事用掛。翌年8月18日の政変に参画し尊攘派勢力を一掃,12月,関白に就任する。
以来,朝彦親王と共に,幕府および徳川慶喜と提携して朝廷を運営,長州再征・条約の勅許に尽力した。慶応2(1866)年9月,列参奏上の22廷臣から批判を受け辞表を提出。却下され,徳川慶喜の将軍就任に力を尽くす。同年12月孝明天皇が没、翌年1月明治天皇の践祚に伴って摂政となる。王政復古の政変で摂政・五摂家の制が廃絶され,参朝停止の処分を受けた。明治1(1868)年8月処分解除,翌年7月麝香間祗候。ちなみに二条家は,他の摂家と違って将軍の諱の1字を用いる慣例があり,斉敬の「斉」は家斉の「斉」である。(「みんなの知恵蔵」より転記)
有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)
天保6年(1835)3月17日生~明治28年(1895)1月15日没
江戸幕末から明治時代の皇族・政治家・軍人。有栖川宮幟仁親王の第一王子。
現在、有栖川宮家は1923年に断絶。東京都港区に有栖川宮記念公園があり、熾仁親王の銅像がある。